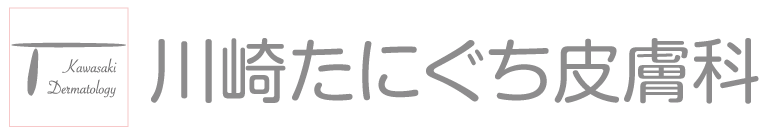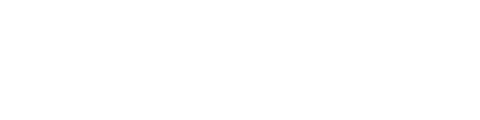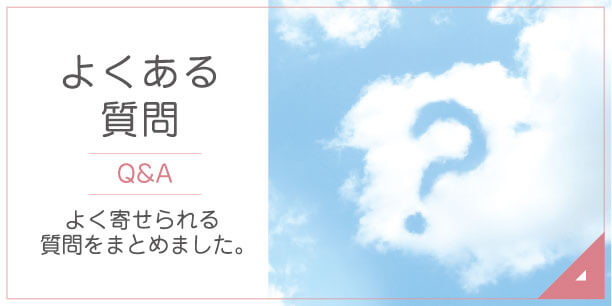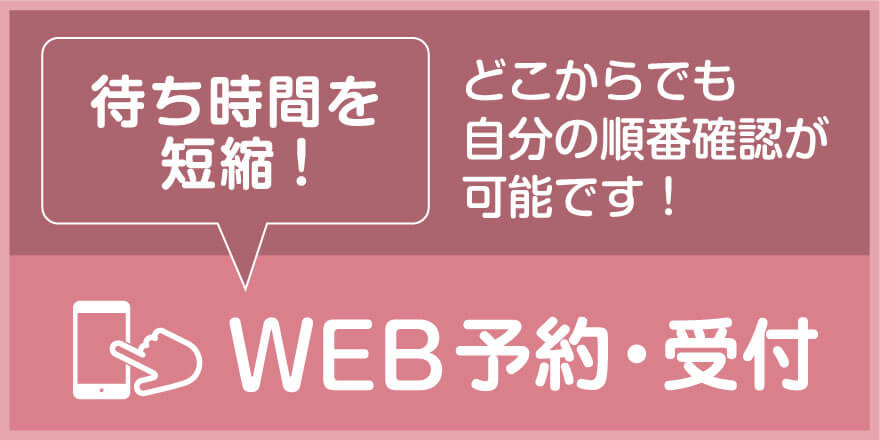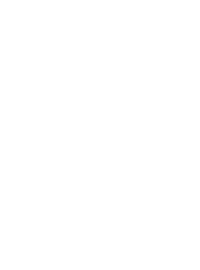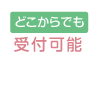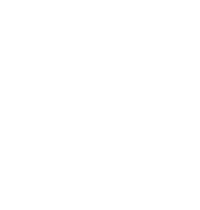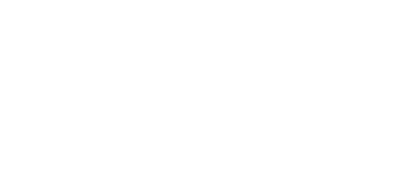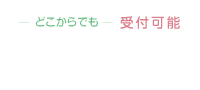「また粉瘤ができてしまった」と繰り返す粉瘤にお悩みの方もいるのではないでしょうか。自然治癒しない粉瘤ですが、適切な予防策と治療法を知ることでできにくい状態を目指すことが可能です。
この記事では、粉瘤を繰り返さないための治療時の注意やセルフケア、治療が必要な粉瘤の症状などについて詳しく解説します。
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
2007年に東京大学を卒業後、東京大学医学部附属病院を中心に総合病院やクリニックで一般皮膚科、小児皮膚科、皮膚外科手術、アレルギー、美容皮膚科領域の診療を行ってきました。その経験・知識を活かし、幅広い医療機器を備えて、様々な皮膚のトラブルの助けになれるよう取り組んで参ります。
粉瘤が再発する原因

粉瘤除去後に再発する原因は、皮膚の下にできる袋状の構造物が手術時に取り残されることです。
粉瘤とは、皮膚の下にできた袋状の構造物の中に垢(角質)や皮脂が溜まってできる良性の腫瘍です。袋が皮膚内に残っていると再び垢や皮脂が溜まり始め、粉瘤が再発してしまいます。
手術で袋の取り残しが起こる理由としては、炎症が非常に強くて応急処置を行った場合、粉瘤が大きすぎる、皮膚の深い場所にあって袋を取り除けなかった場合、医師の技量不足などがあげられます。
とくに、炎症した粉瘤の応急処置では注意が必要です。応急処置は切開を行いますが、袋を取り出さず膿を出すだけの処置となるためです。
当院では、粉瘤の再発が起こらないよう症状に合わせた施術を行っています。
また、粉瘤は、ケガや毛嚢炎(もうのうえん)、ニキビが原因で生じる場合もあります。したがって、毛嚢炎やニキビができやすいといった体質的な要因も、再発に関係があると考えられています。
粉瘤の再発は予防できる?
ここでは、治療時の注意点とセルフケアについて、紹介します。
治療時の注意点
粉瘤の再発を防ぐには、まず治療経験が豊富な医師や医療機関を選ぶことが大切です。袋の取り残しを防ぐためのていねいな手術に対応しているか確認するのも良いでしょう。
大切なのは、炎症を起こす前に治療することです。炎症がない状態の方が袋をきれいに取り除きやすく、傷跡も目立ちにくく、結果的に再発リスクを低く抑えられます。
もし炎症が強い場合は、まず抗生物質などで炎症を抑える治療を優先し、後日改めて袋を除去する手術をすることもあります。術後の消毒やガーゼ交換などは、必ず医師の指示に従ってください。
セルフケア
粉瘤の再発予防において、セルフケアには限界がありますが、悪化させないための注意点は以下のとおりです。
- 自分で必要以上に触らない
- 皮膚を清潔に保つ
- 早期受診を心掛ける
まず、気になっても潰そうとしたり、むやみに触ったりするのは避けましょう。炎症を悪化させたり、細菌が入り込んで感染したりする原因となります。
また、直接的な再発予防策ではありませんが、皮膚を常に清潔に保つことは、毛穴の詰まりや皮膚の細菌感染を予防する上で基本です。粉瘤が発生・悪化するリスクを間接的に低減させる効果が期待できます。
セルフケアで最も重要なのは、粉瘤かなと思ったら放置せず、できるだけ早く医療機関を受診することです。早期受診が、結果的に再発リスクの低い適切な治療につながります。
治療が必要な症状
粉瘤は、自然治癒しない病気です。小さいうち、炎症が起きないうちの治療がおすすめですが、とくに以下のような場合には、速やかに受診してください。
- 徐々に大きくなっている
- 痛み、赤み、腫れがある
- 悪臭がする
- 日常生活で邪魔になる
- 見た目が気になる
- 過去に繰り返している
粉瘤の治療方法
炎症時には切開を行って膿を除去しますが、これは応急処置であり、根本治療ではありません。粉瘤を治療する場合には、以下のいずれかの施術が必要です。
くり抜き法
くり抜き法とは、特殊な器具で粉瘤表面の皮膚に小さな円形の穴を開け、そこから内容物を絞り出した後に、しぼんだ袋状の組織を引き抜く手術方法です。この方法のメリットは、傷跡が小さく、手術時間が比較的短く、体への負担が少ないことです。
ただし、サイズが大きい場合や発生した部位によっては難しい場合があります。また、炎症が非常に強い場合もできません。
メスを使った切除縫縮
切除縫縮は、局所麻酔をした上で、粉瘤本体よりも少し大きく皮膚をメスで紡錘形(葉っぱのような形)に切開し、粉瘤の袋を確実に摘出する方法です。摘出後は、切開した部分の皮膚をていねいに縫い合わせます。この手術の最大のメリットは、袋をまるごと取り除くため、取り残しが起こる可能性が極めて低く、したがって再発リスクが最も低いことです。
一方で、くり抜き法と比較すると、一般的に傷跡が線状に残りやすく、手術時間もやや長くなる傾向があります。また、術後1週間~10日頃に、抜糸のために再度通院していただく必要があります。
粉瘤の施術方法について、詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
当院の治療の特徴
当院では専門医が診察し、状態や患者さんの希望に沿って、最適な手術方法を提案いたします。
施術日以外の来院は、以下のとおりです。
- いずれの方法でも、手術前に感染症の血液検査
- 通常、1週間後に抜糸・傷の診察
- 2週間後に組織検査の結果説明
当院では手術前の検査から術後の経過観察、そして病理診断による確定診断まで、一貫して対応しています。
安心して治療できるよう、万全の体制を整えておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
費用
粉瘤治療は、保険診療が適用されます。部位や大きさによって費用は異なりますが、一般的に以下のとおりです。
処置名 | 費用(保険診療、3割負担) |
手術(検査代含む) | 約10,000円から15,000円(税込) |
|---|---|
切開排膿処置(化膿した粉瘤の場合) | 約2,200円から2,800円(税込) |
よくある質問
Q. 粉瘤は頻繁にできますか?
誰にでも頻繁にできるわけではありませんが、体質的に粉瘤ができやすい方はいらっしゃいます。粉瘤ができる根本的な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、毛穴の構造や詰まり、皮膚への外的刺激などが関係している可能性が考えられています。粉瘤は全くできたことがない方も多く、個人差が大きいと言えます。
Q. 粉瘤を取ったのにまたできたのはなぜですか?
最も可能性が高いのは、手術の際に粉瘤の原因である袋状の組織が完全には取り除かれず、残っていたためです。袋が残っていると、再び垢や皮脂が溜まり始め再発します。
とくに炎症が強い時に治療した場合などは、袋が取りきれずに再発のリスクが高まるので注意が必要です。
まれに、治療した場所のすぐ近くに新しい粉瘤ができた、という可能性も考えられます。いずれにしても、再発した場合は再度、適切な治療が必要です。
Q. 粉瘤は何年くらいで再発しますか?
再発までの期間は、袋の取り残しの程度や個人の体質などによって大きく異なるため、一概には言えません。
手術から数か月で再び膨らんでくることもあれば、数年、あるいは10年以上経ってから再発するケースもあります。
治療後も、しこりや違和感など気になることがあれば、早めに医師に相談してください。
粉瘤の再発を防止したい方は、川崎たにぐち皮膚科へ
粉瘤が再発する原因には、袋の取り残しが考えられます。取り残しが起こる理由としては、粉瘤自体の炎症が強い場合、大きすぎる場合、深い場所にある場合などがあげられます。
粉瘤は、自然治癒しない病気です。疑ったら放置せず、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。早期受診が、結果的に再発リスクの低い適切な治療につながります。
粉瘤の再発を防止したい方は、当院へお気軽にご相談ください。
副作用・リスク
くり抜き法・メスを使った切除縫縮
- 出血、感染、再発、局所麻酔薬のアレルギー反応など